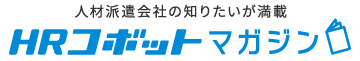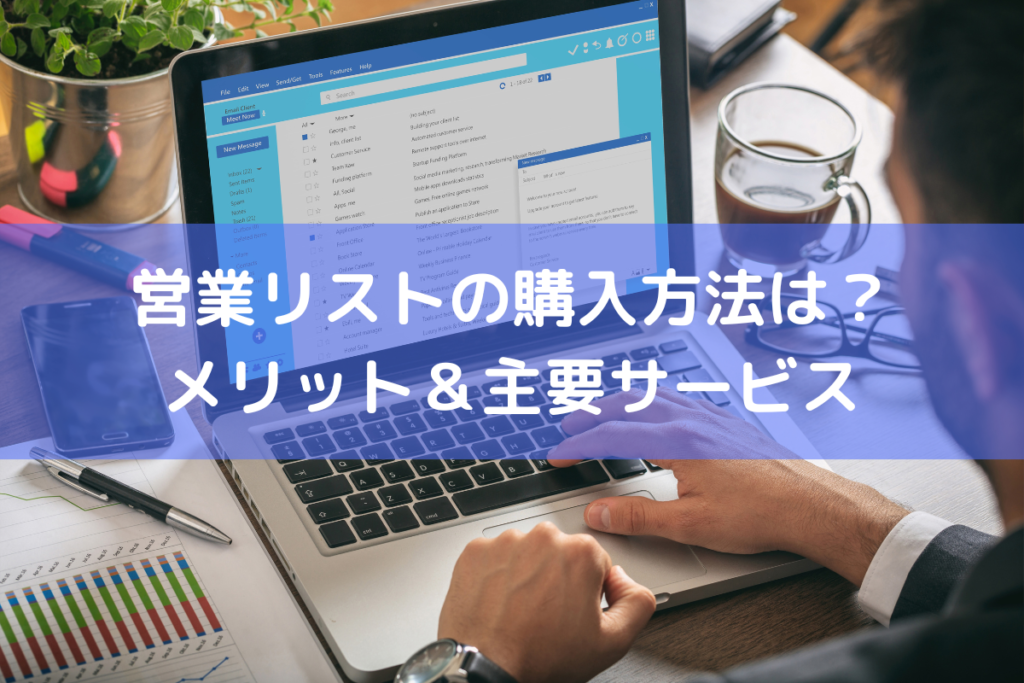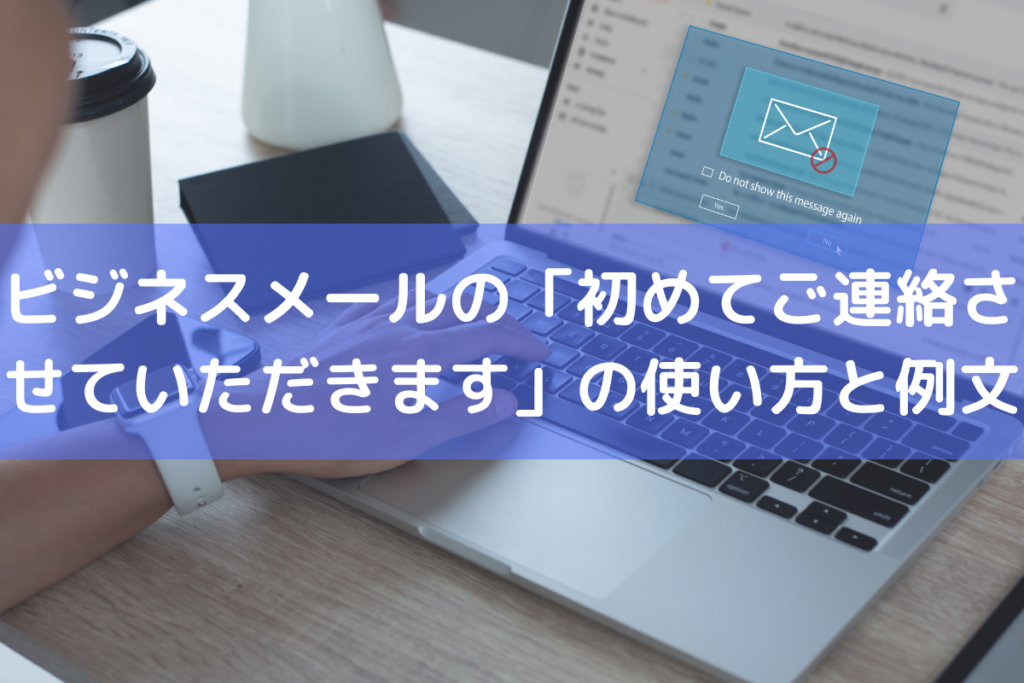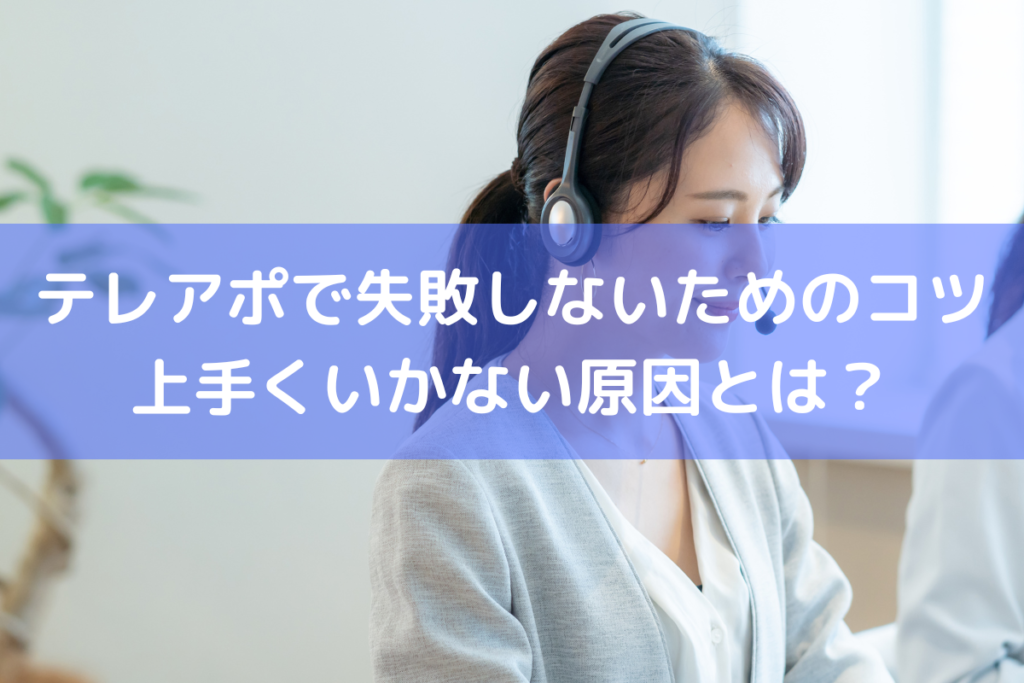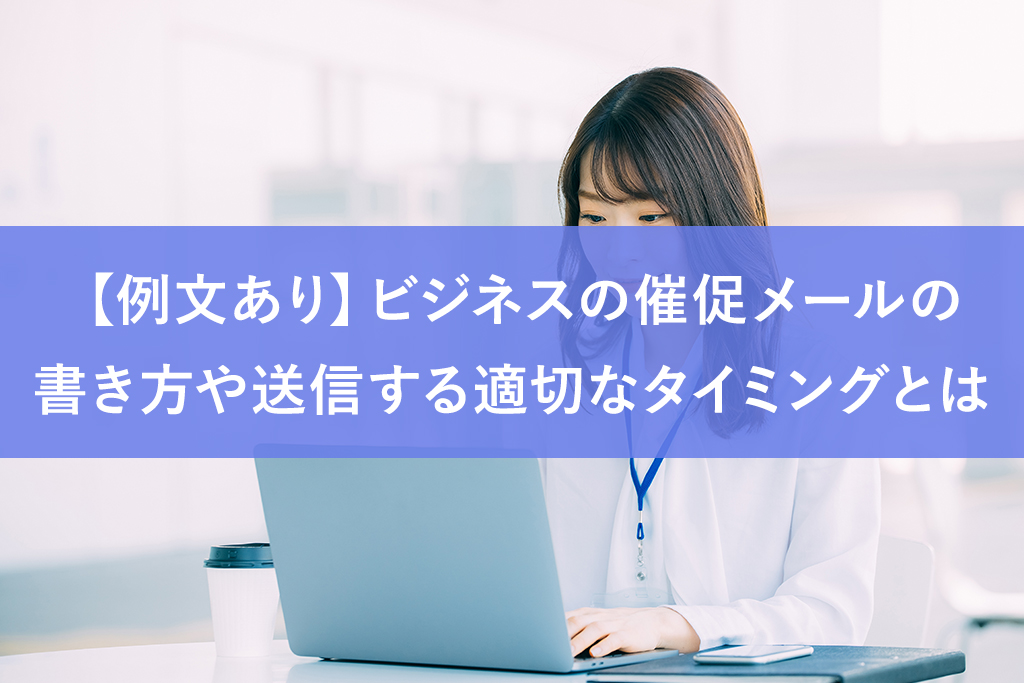
ビジネスで催促メールを送る際は、相手への配慮が欠かせません。文章の表現や送るタイミングなどが難しく、催促メールに苦手意識を持つ方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は催促メールの書き方のコツや、事前に確認しておきたいポイント、催促メールを送るタイミングなどを解説します。ビジネスシーン別の催促メールの例文も紹介しますので、この記事を読めばすぐに適切な催促メールを作成できるようになるでしょう。
ビジネス向け催促メールの書き方のコツ

催促メールの書き方のコツ
- 件名をわかりやすく記載する
- 依頼内容を明確にする
- あらためて期日と催促理由をはっきり示す
- 相手の立場を考慮したフォローで印象アップ
実際に催促メールを送る際、どのような点を意識したらよいのでしょうか?ここでは、ビジネスにおける催促メールの書き方のコツを紹介します。
すでに催促メールの作成が済んでいる場合は、最低限のマナーが守れているかチェックリストとして活用してみてください。
件名をわかりやすく記載する
メールの件名は、一目でわかりやすいものを設定しましょう。相手から確実に期日までの返信をもらいたい場合は、相手の目に留まりやすく、かつ、重要度の高いメール内容だと認識してもらう必要があります。
できるだけシンプルに、具体的に何の要件か伝わるように記載することが大切です。「【 】(すみつきかっこ)」などの記号を利用するのもおすすめです。
【件名の例】
- 「〇〇の件、ご確認のお願い」
- 「【〇〇のご提出のお願い】
- 「【再送】〇〇のご提出について」
このとき、「【入金督促】~」や「【〆切:〇月〇日】~」など、強い印象を与えるキーワードはできるだけ避けたほうが無難です。「【至急】~」なども、相手に対して相当なプレッシャーを与えるため、利用するシーンはよく検討する必要があります。
身勝手な人だと思われてしまい、企業や自分自身の信用を失う可能性があるため注意が必要です。
依頼内容を明確にする
メール文章は、送り先が取引先の場合、文頭や文末に形式的な挨拶を記載し、本題とは直接的に関係のない内容を多く盛り込みがちです。丁寧な表現で記載するために、その内容などがわかりにくくなっているケースもあります。
催促メールでは、相手に「見ていなかった」「わかりづらかった」と言われないために、本題は文頭からシンプルに記載することを心がけましょう。
【依頼内容の例】
- 〇〇の件ですが、その後、進捗はいかがでしょうか?
- 先日お送りしたメールの件、ご確認いただけましたでしょうか?
- 先日お送りした〇〇の件につきまして、本日△△時までにご返信を頂戴する予定でしたが、まだメールが届いていないようです。
依頼内容についても、「~いかがでしょうか」「~のようです」などやわらかい表現を使い、相手にプレッシャーを与える表現は控えましょう。逆に、今後の取引にかかわるような重大な内容であれば、あえて強い印象を与える表現を利用するなど、状況に応じて言葉選びを工夫しましょう。
あらためて期日と催促理由をはっきり示す
催促メールでは、あらためて期日を伝えることはもちろん、催促をする根拠・理由についても明確に記載をしましょう。理由を明示しないまま期日を設定することは、忙しい相手にとっては、期日を設定する側の都合であり身勝手とも思われかねません。
【期日・催促理由の例】
- ~の開催が明日に迫っているため、本日〇月△日の17時までにご返信をお願いいたします。
- ~の発注が週末までに完了できない場合、発表していた日程での販売開始が難しくなることが見込まれるため、遅くとも〇月△日の□時までにはご回答をお願いいたします。
催促の理由は、できるだけシンプルに記載しましょう。あまりに切羽詰まった状況を伝えてしまうと、逆にそもそもの期日設定や進捗管理に問題があったのではないかという指摘を受けてしまうため注意が必要です。
相手の立場を考慮したフォローで印象アップ
期日までに相手から返信が来ていなかった場合も、相手が何らかの方法で意思表示をしていたという可能性も考えられます。万が一、行き違いとなっていた場合の可能性も考慮し、文末には相手の立場をフォローするような一言を添えましょう。
【フォローの例】
- なお、本メールと行き違いとなってしまった場合は、大変申し訳ございません。
- なお、本メールと行き違いとなり、すでにご対応・ご返信いただいておりました場合は、何卒ご容赦ください。
催促メールを送る前に確認しておきたい4つのポイント

催促メールを何も考えずに送信することは危険です。何も考えず催促メールを送ってしまうと、逆に自分自身が指摘を受けてお詫びをすることになり、相手からの信頼を失ってしまう可能性もあります。
催促メールを送る際、事前に確認しておくべきポイントを紹介します。
ポイント
- メールや案内は確実に送られているか?
- 相手からの返信メールや送付物を見逃していないか?
- 明確に期日を設定していたか?
- 催促メールではなく電話で確認できないか?
メールや案内は確実に送られているか?
相手に対して催促メールを送る際は、まずは「そもそも自分が依頼した内容が、しっかりと相手に伝わっているか?」という意識を持って事前確認を行なう必要があります。
- 送信メールの宛先は間違っていないか?
- 送信したメールは、未送信ボックスに入っていないか?
- 第三者に伝言で依頼していた場合、相手に確実に伝言されているか?
- 自分や会社から送付した郵送物は、相手に確実に届いているか?
メール・口頭伝達・伝言・郵送など、ビジネスにおける依頼の方法はさまざまです。自分に落ち度がないかという視点はもちろん、相手に確実に伝わっているかという視点を持つことがポイントとなります。
メールの場合、相手の迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性や、相手の事情によってまだメールを開封できていない状況も考えられます。つまり、期日までに返事やリアクションをすることの同意を、相手から直接取り付けられていない限りは、コミュニケーションが一方通行になっている可能性があることを考慮する必要があります。
もちろん、こうした考慮は、あくまで想像の域に過ぎません。しかし、催促メールを送信する前に、相手側の状況について想像することは、相手が返信しやすい文章、相手に配慮した文章を作成するテクニックとして活かすことができます。
相手からの返信メールや送付物を見逃していないか?
催促メールを送る前に、すでに返信メールや返送物(書類などの送付物)が届いていないか確認しましょう。
自分の送信メールが「相手のメールボックスの迷惑フォルダ」に入っている可能性があるのと同時に、相手の送信したメールが「自分のメールボックスの迷惑フォルダ」に入っている可能性もあります。
最近では、多くの企業がさまざまなセキュリティ対策を行なっているため、なんらかの事情でメールの受発信に問題が発生しているケースも珍しくはありません。
また、相手が特定の人にだけメール返信をしていたというケースも考えられます。自分の発信メールの宛先に複数名が入っていた場合、確認できる範囲で「〇〇さん(メール返信が欲しい相手)から、返信メール届いていませんか?」と、念のためチェックをしましょう。
明確に期日を設定していたか?
ビジネスでは、「期限までに返信・対応することは社会人としてのマナー」「遅れるのであれば、事前に連絡・相談をすることがマナー」といった共通認識があります。
一方で、ビジネスでは相手の立場や関係値も考慮したうえでメール送信を行なう必要があります。
期日を設定していた場合は、その期日設定が適切なものだったのかなど、相手の立場を考慮する気持ちも必要です。相手の状況を想像することで、催促メールを送信する際、相手に配慮した文章を作成できます。
また、依頼する内容によっては、期日を明確にしておくことがふさわしくないケースもあります。期日を記載していなかった場合、催促メールには、期日を明確にしてなかったことについてお詫びをする文言を入れ、あらためて具体的な期日とその理由について記載してください。
催促メールではなく電話で確認できないか?
催促メールを送信する前に、そもそもメールで催促を行なう必要があるかを検討することも大切です。つまり、電話で確認を済ませることができないか、社内であればオフィスで会った際に口頭で確認することができないかといった点についても検討してみてください。
メールによるコミュニケーションはメリットもありますが、デメリットもあります。催促メールを受け取った相手の性格や立場によっては、「催促メールを送られた」「しかも、関係者に共有され、恥をかかされた」と感じる人もいるでしょう。
また、メールでのコミュニケーションは、「メールボックスを確認する」→「メールの内容を読んで内容を理解する」→「返信メールを作成し、送信する」という複数の動作が発生します。そのため、タイミングによっては、相手が面倒だと感じてしまうケースもあります。
一方、メールだからこそのメリットもあります。例えば、「なかなか相手に会える機会がない」「相手が忙しくてオフィスにいない」といった場合にメールは効果的です。
さらに、「メールの写しに関係者を入れて多くの人とメール内容を共有するからこそ、返事をもらえる可能性も高くなる」といったメリットもあります。メールのメリット・デメリットを理解したうえで、有効的に催促メールを送りましょう。
ビジネス向け催促メールを書く際の注意点

催促メールでの注意点は、「催促メールに対して、相手がいかに返信しやすいメールを作成するか」という配慮を忘れないということです。正義感の強い人ほど、催促メールがとげとげしい文章となり、受け取った相手を不快に感じさせる傾向にあるため注意が必要です。
注意点
- 相手のリアクションのしやすさを意識する
- やんわりとした文章表現を心がける
- リアクションがあった際は速やかにお礼と返信を送る
相手のリアクションのしやすさを意識する
催促メールの文章に相手を責めるような内容の表現があると、受け取った相手は返信に困ってしまいます。相手の返信はさらに遅くなってしまうため、これでは催促メールの意味がありません。
また、次のようにあらゆる点を考慮すれば、自分側に一切の責任がないとは言い切れない可能性も十分にあります。
- 依頼内容が確実に相手に伝わっているか
- 連絡が行き違いになっていないか
- 期日設定についても相手を配慮したうえで、明確な設定理由を示すことができていたか
- 依頼したメール内容はわかりやすい文章であったか
そのため、よほど重大な事態に陥っていない限り、催促メールは、相手が気持ち良くすぐに返信できるような文章を作成することが大切です。文末などにやわらかい表現の文章を添えて、相手への理解の気持ちを示しましょう。
【リアクションのしやすさ意識した例】
- 「本メールの内容に不備・不明点などがありましたら、お気兼ねなくお知らせください」
- 「ご対応・ご返信にあたり、わかりづらい点などがあれば、メールでもお電話でもお気軽にお問い合わせください」
やんわりとした文章表現を心がける
断り・反論・否定・指摘など、そのまま伝えると相手に対して不快な印象を与えてしまう可能性がある言葉の前に、「クッション言葉」を使いましょう。
クッション言葉とはその名のとおり、「クッション」的な役割を果たし、本題のネガティブな内容をやんわりと相手に伝えることができます。
【クッション言葉の一例】
- 「お忙しいなか大変恐れ入りますが」
- 「ご多忙中のことと存じますが」
- 「お手数をおかけしますが」
- 「誠に恐れ入りますが」
- 「ご面倒をおかけしますが」
リアクションがあった際は速やかにお礼と返信を送る
催促メールは、相手からの回答を得ることばかりに意識が向いてしまいがちです。相手から返信をもらったら、次は作業を進めることばかりに意識が向いてしまい、返信をスルーしたり、適当な返信をしてしまったりというケースも珍しくありません。
社内の同僚や部下に対してはそれでも問題ないかもしれませんが、取引先ともなると、ビジネスパートナーとしてふさわしいマナーが求められます。返信を受け取った際は、すみやかにお礼と感謝を伝えることで、今後の良好なコミュニケーションにつなげられます。
返信内容については、回答の内容によってさまざまなシーンが想定されますが、「お忙しいなか、ご返信(ご対応)いただきありがとうございました」という感謝を表すフレーズは忘れないように記載しましょう。
ビジネスシーン別の催促メール例文
次に、ビジネスにおけるさまざまなシーンを想定した催促メールの例文を紹介します。実際に使う際は、例文をベースにしつつアレンジを加えてご活用ください。
回答や返信が来ないときの催促メール
まずは、最も基本的な催促メールの例文です。相手に対しプレッシャーをかけない程度に、回答を急ぐ理由も記載しましょう。「~できますと幸いです」といった、やんわりとした表現を使うこともポイントです。
先日ご回答をお願いした△△の件につきまして、その後、ご確認いただけましたでしょうか?
△△の開催が明日に迫っている都合上、ご回答いただきたく連絡を差し上げました。
お忙しいなかお手数をおかけしますが、〇月〇日〇時までにご回答いただけますと幸いです。
ご回答にあたり、ご不明点・ご質問などございましたら、お気兼ねなくお問い合わせください。
2回目の催促メール
次に、催促の連絡をしてもまだ回答をしてもらえず、ふたたび催促メールを送る際の例文です。重要度にもよりますが、回答を急ぐ気持ちを抑えつつ、相手側への配慮の気持ちを示すフレーズも差し込みましょう。
先日、ご回答をお願いした△△の件で、あらためて連絡しました。
〇月〇日までのご回答をお願いしておりましたが、その後、いかがでしょうか?
ご多忙のためメールをご確認いただけていない可能性もあると思い、念のため再送させていただきます。
追って電話でも確認の連絡を差し上げる予定ですが、〇月〇日〇時までにご回答いただきたく、ご協力のほど何卒お願いいたします。
書類確認の催促メール
書類の場合、サイン・返送など受け取る側の対応・作業が必要となるケースも多くあります。送付した書類の重要性について触れつつ、さらに相手側のアクションを促すような一言も加えるとよいでしょう。
また、書類などのやり取りは、受け取りに時間差が発生する可能性もあります。そのため、行き違いとなっている可能性についても文章に盛り込みましょう。
先日送付をさせていただいた〇〇の書類ですが、無事△△様のお手もとに届いておりますでしょうか?
〇月〇日の時点で、まだ当社にご返送の確認がとれていなかったため連絡しました。
こちらの書類は、〇〇のご契約にあたり、〇月〇日までに必ずご提出いただく必要がございます。期日までのご提出につきまして、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご記入・ご返送にあたり、ご不明点などがございましたらお気兼ねなく以下の連絡先までお問い合わせください。
TEL:〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇(営業時間:〇〇~〇〇/担当:〇〇)
なお、すでに書類をご返送いただき、本メールと行き違いになっている場合は何卒ご容赦ください。
入金の督促メール
依頼した期日までの入金が確認できなかった場合、取引先に対して、入金の督促メールを送ることとなります。
ただし、相手が個人ではなく企業の場合、請求書を送付した担当者は、請求書の処理手続きを自分自身で行なっていないケースもあります。相手企業の経理担当者の手違いなどの可能性なども踏まえ、督促メールとはいえ相手を不快にさせないよう心がける必要があります。
〇〇の代金のお支払いにつきまして、〇月末日付にて請求書をお送りさせていただきましたが、〇月〇日時点でご入金の確認ができていない状況です。
お忙しいなか大変恐れ入りますが、振り込み状況をご確認いただき、未納の場合にはあらためて〇月〇日〇時までにお振込みのご対応をお願いいたします。
念のため、下記にお振込み金額・お振込み先を記載いたします。
【お振込み内容】
・金額:〇〇〇〇円
・振込先:〇〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇〇〇
お手数ですが、ご入金後、本メールにご返信いただけますと幸いです。
なお、本メールと行き違いでお振込み済みの場合は、何卒ご容赦ください。
催促メールを送るタイミング
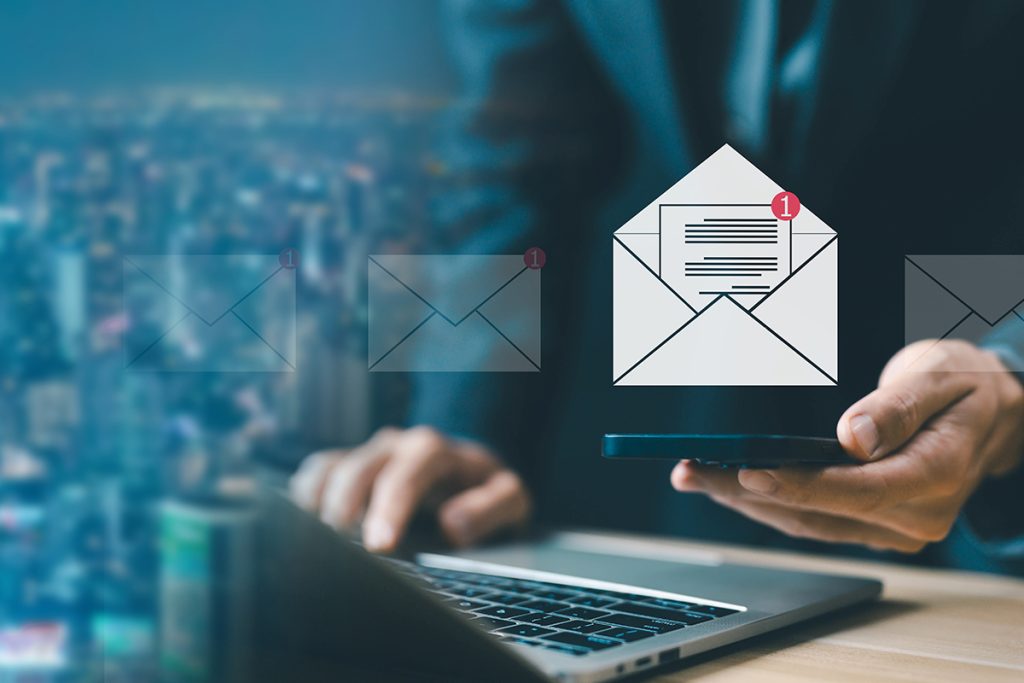
催促メールを送るタイミングを誤ると、相手との関係が悪化する可能性があるため細心の注意が必要です。催促メールを送る適切なタイミングを紹介します。
納品物や書類の到着に遅れが生じているとき
納品物や書類の到着が予定よりも遅れているときは、催促メールで送付状況を確認しても失礼にはなりません。到着の遅れは、出荷遅延などの配送トラブルに巻き込まれている可能性があり、そのまま放置するとさらに到着が遅れる可能性があります。したがって、催促メールを送って状況を確認することが大切です。
ただし、事前に期日を設定していないときは、催促メールの送信タイミングが早すぎると相手に負担をかける可能性があります。この場合は、特にやわらかい表現を使うなどの配慮が必要です。
入金の確認が取れないとき
入金の確認が取れないときは、請求書が届いていないケースや、相手が入金先を間違えている可能性などが考えられます。相手が企業の場合は、相手方で何らかのトラブルが起きている可能性も考えられるため、できるだけ早めに連絡しましょう。
一方で個人が相手の場合は、単に入金を忘れている可能性があります。こちらに余裕があれば2~3日猶予をおいてから連絡しましょう。
いずれにしても、トラブルの内容によっては手続きで入金がさらに遅れる可能性があるため、早めの連絡が大切です。
メールの返信が届かないとき
一般的にビジネスメールへの返信は当日中が望ましく、遅くとも24時間以内に返信したほうが良いとされています。しかし、24時間を経過したからといってすぐに催促メールを送ると、相手に負担をかけるおそれがあります。ほかの仕事が忙しいなど、すぐに返信できない理由が相手にあるかもしれないからです。そのため、2日や3日など一定の基準を決めておき、その基準を過ぎた時点で催促メールを送るとよいでしょう。
また、メールの返信が来ない理由の一つとして、送信エラーでそもそもメールが届いていないケースが考えられます。この場合は催促メールも届いていない可能性が高いため、催促メールにも返信がない場合は電話で確認しましょう。
催促メールを適切なタイミングで送る方法
催促メールを適切なタイミングで送るために、CRM(顧客関係管理)ツールの導入をおすすめします。CRMは顧客の氏名やメールアドレスなどに加えて、メールに関する管理も可能です。メールの配信状況を記録するだけでなく、タスク管理や通知設定もできます。
また、CRMによっては顧客のアクションに応じたメール配信が可能です。タスク管理や通知を利用すれば、催促メールを送るタイミングを自動的に把握でき、業務が効率化されます。
まとめ
催促メールは表現がきつくなってしまいがちですが、やわらかい表現を使って相手が返信しやすい文章にすることがポイントです。今回紹介した催促メールの書き方や例文を参考に、適切なメールを作成しましょう。
また、催促メールを送るタイミングを誤ると、相手との関係性が悪化するおそれもあるため注意しましょう。しかし、顧客が多いと、誤ったタイミングで催促メールを送ってしまうこともあるでしょう。顧客の管理に困っている場合にはCRMの導入がおすすめです。
CRMを導入するなら「HRコボット for 営業リスト」をぜひご検討ください。
「HRコボット for 営業リスト」は人材派遣会社の営業リスト作成に特化したツールです。短時間かつ自動で営業リストを作成できるなどの強みをもっています。
初期費用55,000円から運用可能となっています。
詳しい内容はこちらの問い合わせフォームよりお問い合わせください。