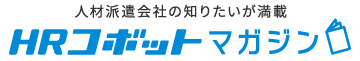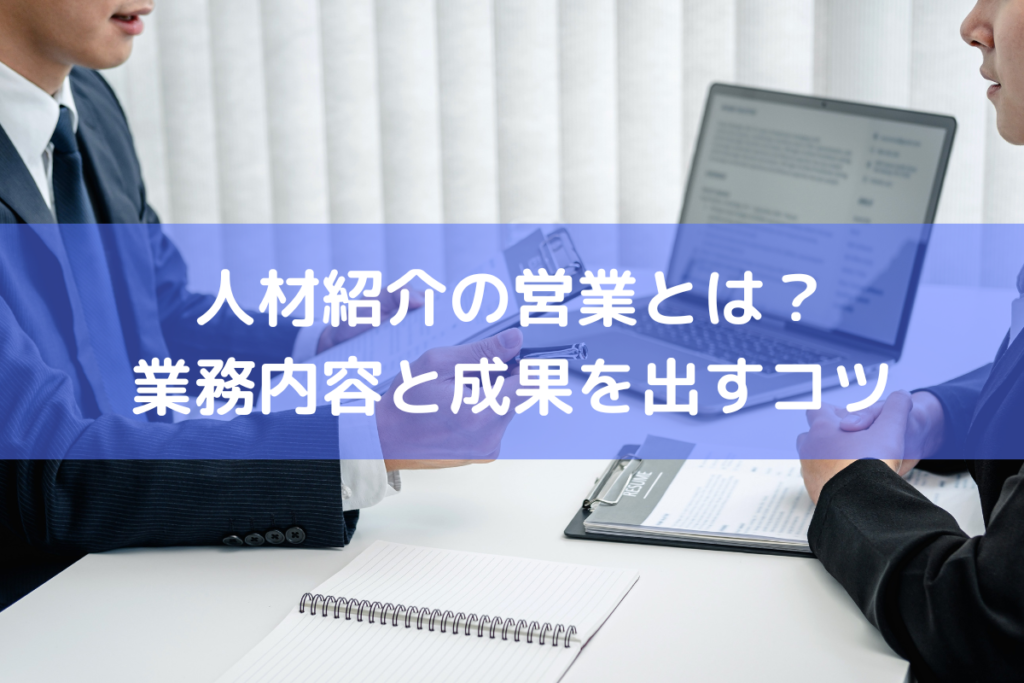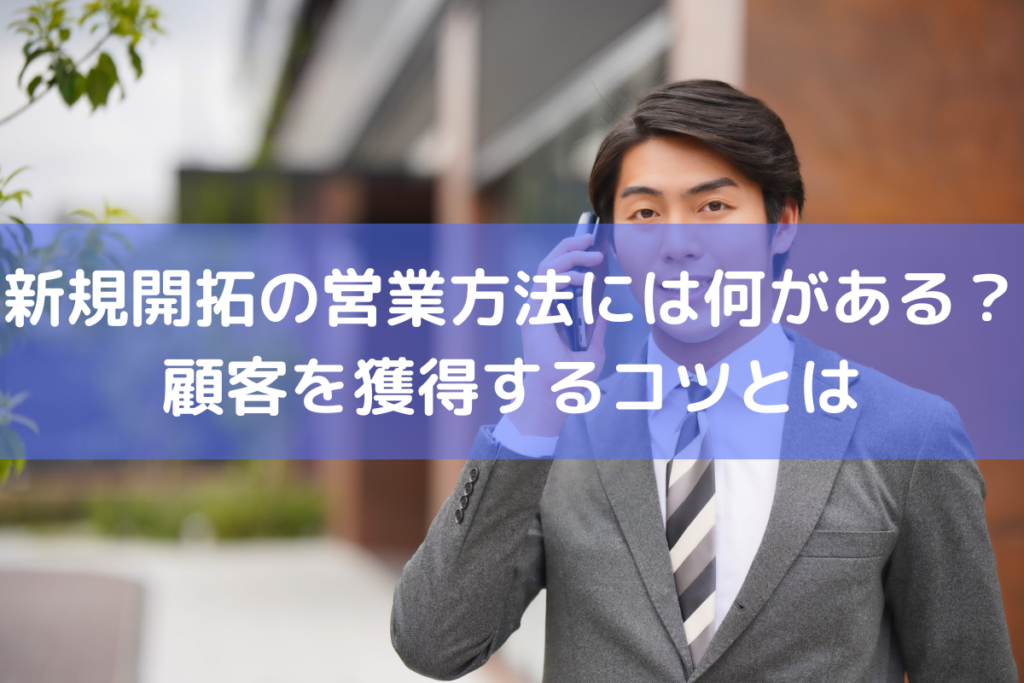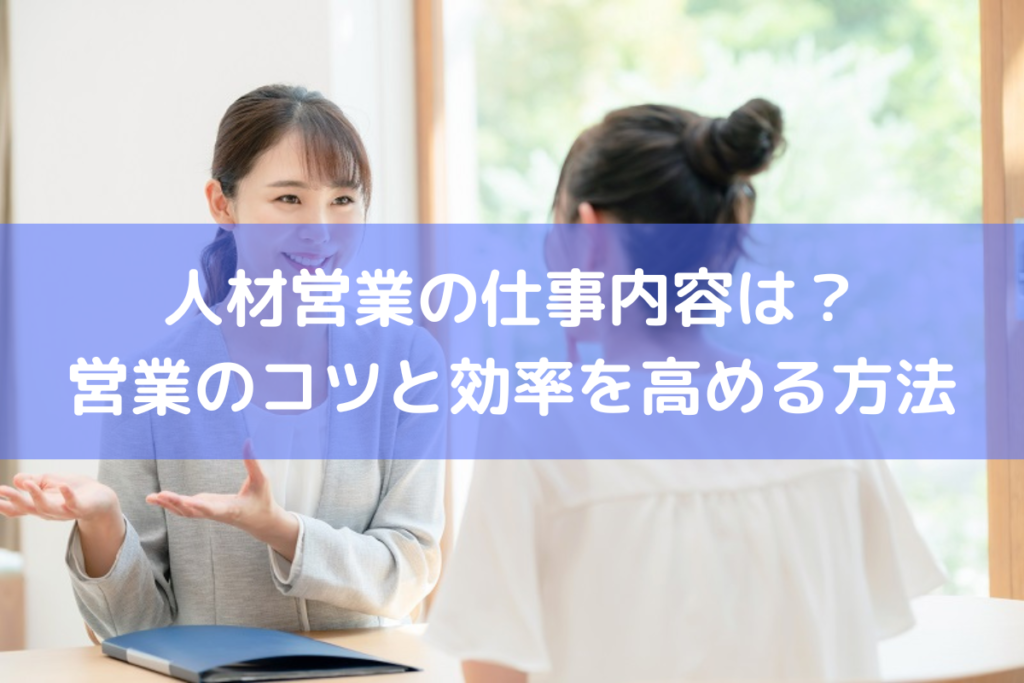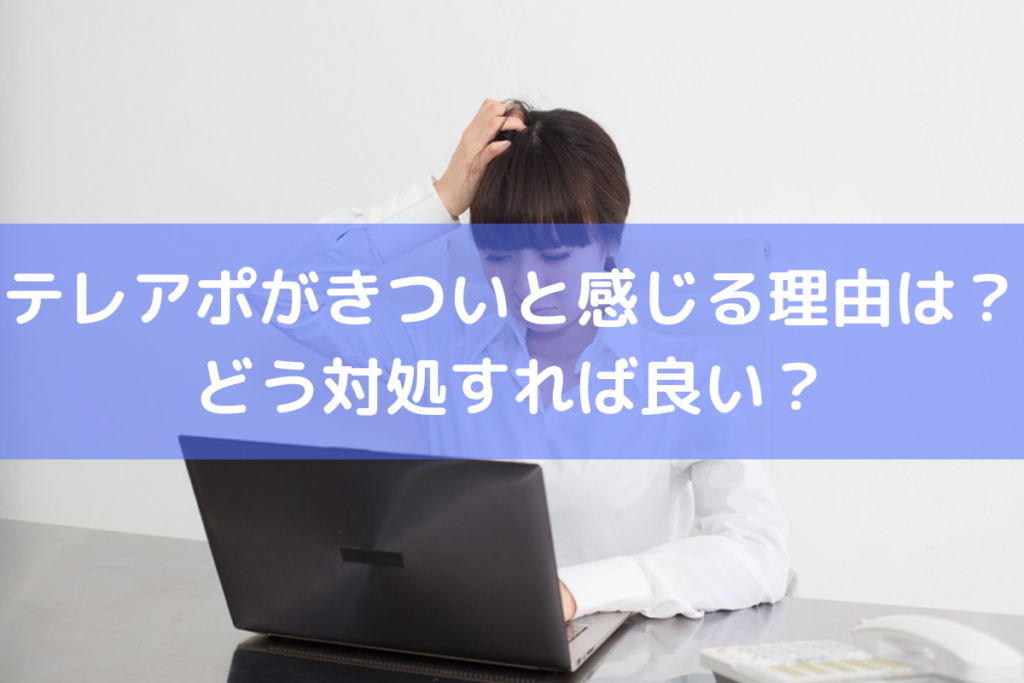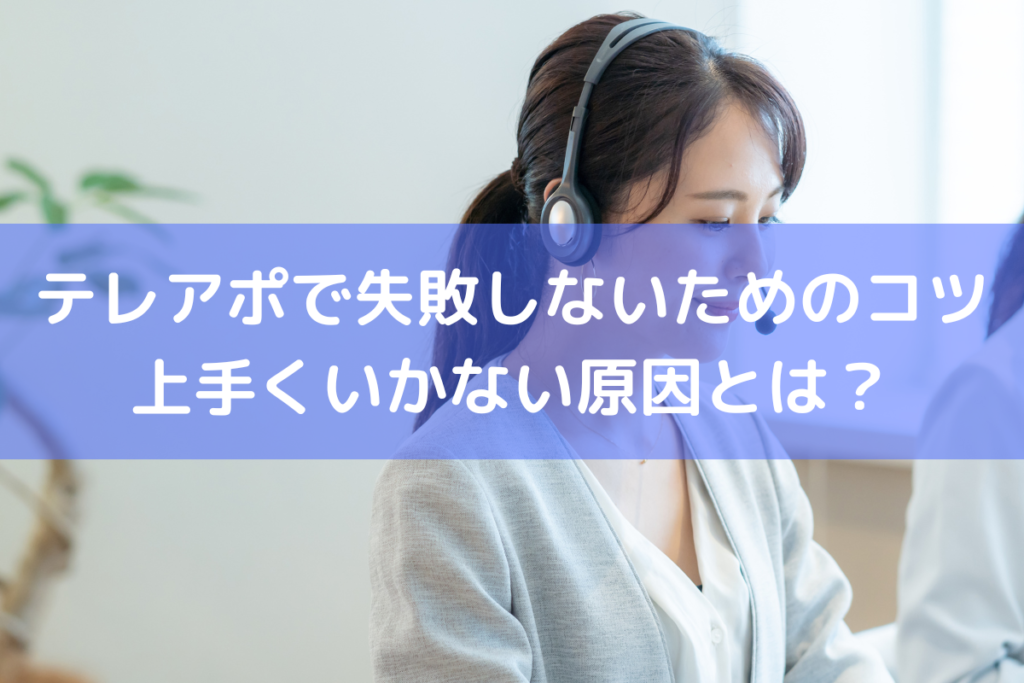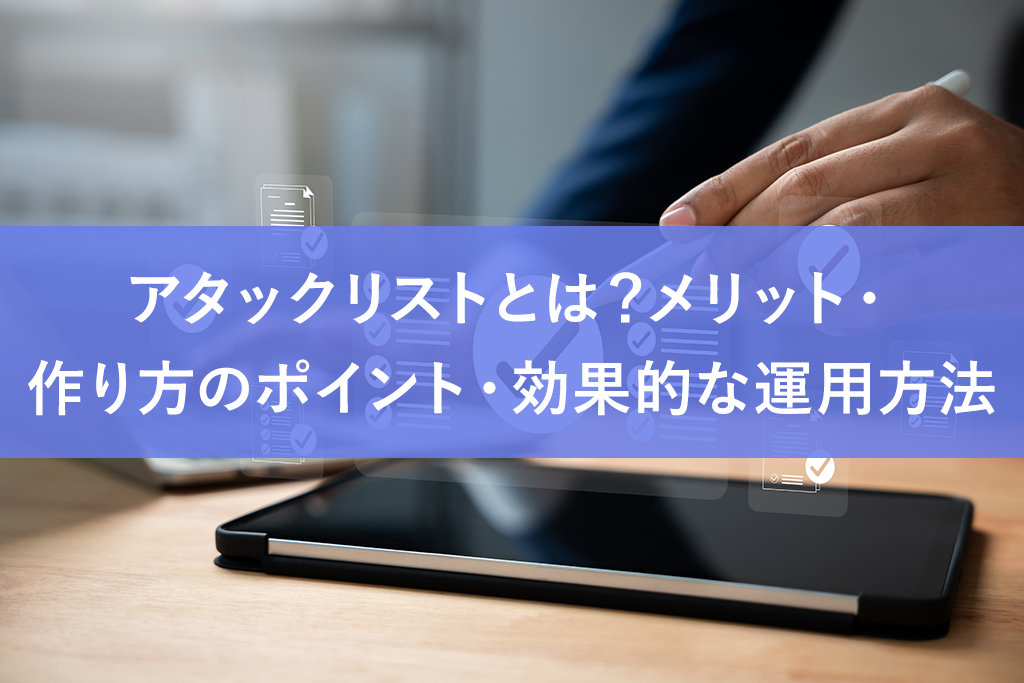
営業活動を進めるなかで、「アプローチ先をうまく絞り込めない」「成果に結び付けるリストを作りたいのに、どうすれば良いかわからない」と感じることはありませんか?
こうした課題を抱える方にとって、心強い味方になるのが「アタックリスト」です。ただし、リストを作るだけでは成果にはつながりません。どのような準備が必要で、どのように作り、活用していけば良いのかを理解することが大切です。
この記事では、アタックリストの基本やメリット、作り方、運用のポイントを丁寧に解説します。営業活動の課題解決にぜひお役立てください。
アタックリストとは
アタックリストは、営業をかけることで何らかの成果が期待できると考えられる顧客情報をまとめたリストのことです。
アタックリストの呼び方は企業によって異なり、「顧客リスト」や「営業リスト」、「ターゲットリスト」などと呼ばれています。いずれにせよ、アタックリストの目的は変わらず、闇雲な営業活動を避け、自社や自社製品に興味を持ってくれそうなターゲット情報をまとめるために作成します。
リストをなぞるだけで高い営業効果を発揮できる必要があるため、作成の際にはある程度のノウハウと時間が必要になります。
アタックリストを作る理由

アタックリストは営業活動に絶対必要というわけではありませんが、時間や労力を無駄にしない営業を実現するうえでは非常に効果的です。アタックリストが活躍する理由には、次の2点が挙げられます。
| 理由 ・営業活動は属人化しやすいため ・データ活用の手段が多様化したため |
営業活動は属人化しやすいため
1つ目の理由は、営業活動の属人化のしやすさです。
事務作業とは異なり、営業業務は、その大半を見込み客とのコミュニケーションや関係構築に割く必要があるため、担当者の営業スキルに出来高が大きく左右される傾向にあります。
そのため、人と仲良くなるのが得意な人や、年月をかけてコネクションを構築している人、巧みな話術で成約を得られる人など、トップのセールスパーソンは高い成果を創出できる一方で、トップ層ほどの技術を持たない担当者は成果をなかなか得られず、コツがつかめるまでに時間がかかるというケースもあります。
トップ層とそうでない層のギャップが激しいため、トップ層が不調のときや退職してしまったときには営業成績が落ち込んでしまい、事業の成長が停滞するリスクがあります。
アタックリストの作成は、このような営業担当者の能力のギャップを解消し、属人化を回避する役割を担います。見込みの高いターゲットをリスト作成の過程でピックアップできれば、ずば抜けた営業能力はなくとも成約に結び付けやすくなります。
データ活用の手段が多様化したため
2つ目の理由は、データ活用手段の多様化です。
今日では、多くの企業でデータ活用が進んでいますが、これを促進したのがデジタルツールの登場です。さまざまなITサービスを駆使して見込み客の行動を見える化することで、企業は行動履歴に基づく見込み客の関心度合いを数値に落とし込めるようになりました。
ツールを導入することによって、問い合わせ履歴やメールマガジンの開封率など、見込み客の一挙一動が手に取るようにわかります。
こういった情報を参考にすることで、アタックリストはただの情報の羅列ではなく、成約率アップにつながる厳選されたリストとして多くの組織で活躍しています。
アタックリストを作成するメリット
精度の高いアタックリストの作成は、営業活動に複数のメリットをもたらしてくれます。ここでは、おもな5つのメリットについて解説します。
| メリット ・営業活動を効率化できる ・営業成績が安定する ・組織的なデータ活用を促進できる ・顧客への継続提案につなげられる ・見込み客や既存顧客の分析に役立つ |
営業活動を効率化できる
1つ目のメリットは、営業活動を効率化できることです。
あらかじめアタックリストを用意しておくことで、営業担当者はリストに則ってアプローチすれば一定の成果を期待できるため、「誰に営業をかければ良いのか?」というところから頭を悩ませる必要がなくなります。
効率的に興味を持ってくれそうなターゲットを探すことだけに集中できるため、営業スピードの向上が期待できます。
営業成績が安定する
2つ目のメリットは、営業成績が安定することです。
アタックリストは、成約見込みの高そうなターゲットに絞って情報をリスト化しているため、極端に成約が得られない日が出てきてしまうことを回避できます。
見込みのありそうなターゲットに絞っているとはいえ、必ず成約が得られるとは限らないものの、手当たり次第にアプローチをかけるよりは成績を得られやすい環境を整備できます。
組織的なデータ活用を促進できる
3つ目のメリットは、組織的なデータ活用を促進できることです。
作成したアタックリストは、特定の担当者だけが利用するのではなく、営業担当者全員で共有する形で運用することが一般的です。そのため、見込みのあるターゲットに関する情報が特定の営業担当者のコネクションに依存しなくなります。まだ業界経験が浅く、情報網も構築できていない若手の営業担当者でも確度の高いターゲットに近づけるようになります。
見込み客の情報も企業が所有するデータ資産として扱い、組織の利益のため社員に共有できる環境を構築することが、アタックリスト作成に求められる条件です。
顧客への継続提案につなげられる
4つ目のメリットは、顧客への継続提案につなげられることです。
アタックリストには、初回アプローチ時の顧客の反応や当時の状況を詳細に記録しておけます。これにより、時間が経過したあとでも、以前のやり取りを振り返りながらスムーズに会話を再開できるようになります。
さらに、顧客のニーズが変化している場合でも、過去のやり取りを参考にしながら適切な提案を行ないやすくなります。こうしたデータの活用は、顧客との関係維持や継続的な営業機会の創出に大きく貢献するでしょう。
見込み客や既存顧客の分析に役立つ
5つ目のメリットは、見込み客や既存顧客の分析に役立つことです。
アタックリストには、顧客の反応や担当者に関する情報が蓄積されていきます。これらの情報をもとに、成約につながりやすい顧客の特徴や傾向を分析できるようになります。
また、分析結果を活用してアプローチ先の優先順位を見直すことで、営業活動の精度を一層高めることが可能です。
このようにアタックリストは、営業の進め方を見直し、より効率的な活動へと導く重要なデータ基盤になります。
アタックリスト作成前に取り組むべき準備

アタックリストを作成する前に、いくつかの準備を進めておくと営業活動全体の精度を高められます。ここでは、準備のポイントを5つ解説します。
| 作成前の準備 ・市場環境や競合状況を調べる ・自社の営業課題を洗い出す ・自社の強みや提供価値を言語化する ・営業戦略を固める ・具体的な営業アプローチの流れを設計する |
市場環境や競合状況を調べる
アタックリストの作成に入る前の第一歩として、市場環境や競合状況の調査を行ないましょう。
市場のトレンドや顧客ニーズの変化をしっかり把握し、競合他社の動きや自社の立ち位置を客観的に確認することが大切です。こうした情報を整理することで、アタックリストに盛り込むターゲット候補や営業アプローチの方向性をより明確にできます。
市場や競合の状況を理解したうえでリストを作ることで、より効果的で無駄のない営業活動を展開できます。
自社の営業課題を洗い出す
市場や競合の状況を踏まえたうえで、自社のシェアや販売実績を客観的に確認し、営業上の課題を洗い出すことが重要です。
こうした課題を整理する際には、「SWOT分析」や「3C分析」といったフレームワークを活用すると便利です。
SWOT分析は「Strength(強み)」「Weakness(弱み)」「Opportunity(機会)」「Threat(脅威)」の4つの要素から構成されるフレームワークで、外部環境と内部環境などを組み合わせて分析します。業界や市場を理解し、自社の立ち位置や取り組むべき行動を明確にできます。
一方、3C分析は「自社(Company)」「競合(Competitor)」「顧客(Customer)」の3つの視点を明らかにし、営業活動における効果的な方法を検討する手法です。自社の強みや競合のシェア・弱点、顧客が求めるものを調査し、具体的な施策に落とし込みます。
自社の強みや提供価値を言語化する
競合他社にはない自社の技術力やブランド力、顧客満足につながる特徴を明確にし、強みとして言語化しておくことが大切です。自社の強みを具体化することで、差別化ポイントがはっきりし、アプローチ方法や営業戦略に活かしやすくなります。
強みの把握には、先に紹介したSWOT分析や3C分析も役立ちます。こうした分析を通じて、自社の魅力を言語化し、営業活動全体の方向性を具体的に描きましょう。
営業戦略を固める
市場環境や競合状況、自社の営業課題、そして自社の強みや提供価値を整理したあとは、それらを踏まえた営業戦略をしっかり固めることが大切です。
営業戦略が明確であれば、リストに含むべきターゲットを具体化しやすくなります。アタックリストの精度向上のためにも、戦略的な営業プロセスを確立することが欠かせません。
具体的な営業アプローチの流れを設計する
営業アプローチの具体的な流れを設計する準備も整えましょう。テレアポや訪問営業、DM営業、SNS活用、Webサイト運営、展示会やセミナーの開催など、どの手法をいつ使うか、どの順番で進めるかを事前に決めておくことが大切です。
アプローチの流れを具体的に設計することで、営業活動の無駄を減らし、アタックリスト作成や情報収集の精度向上にもつなげられます。こうした設計が、成果を出す営業活動へと直結します。
アタックリストの作り方

アタックリストのメリットや作成前の準備を理解したうえで、ここでは具体的なアタックリストの作成方法について確認しましょう。
アタックリストの作成においては、次の6つのステップを踏まえることが大切です。
| アタックリストの作り方 ・ターゲットを定める ・ターゲットの情報を収集する ・リスト項目を設計し情報をまとめる ・入力ルールやフォーマットを統一する ・補足情報を記載できる項目を用意する ・リストに必要な情報を登録する |
ターゲットを定める
1つ目のステップは、ターゲットを明確に定めることです。
アタックリストを作成する目的は、成約率の向上につながるターゲットをピックアップしてリスト化することにあります。そのためには、まずどのような人物や組織をターゲットとするかということから考える必要があるでしょう。
適切なターゲット選定を進めるうえでは、営業活動を通じてどういった商品を成約につなげたいのかということを念頭に置きます。自社商品の強みやアピールポイント、世間ではどのようにその商品が評価されているかを客観的に評価するところから始めることが大切です。
自社や自社商品が世間でどのように評価されているか、どのようなニーズに応えられそうかを正しくとらえられれば、自然とアプローチすべきターゲットのイメージも具体的に固まっていきます。
ターゲットの情報を収集する
2つ目のステップは、ターゲット情報の収集です。
アプローチすべき相手がわかったあとは、ターゲットに対してどのようにアプローチすれば良いのかを検討するための情報を集める必要があります。ターゲットのニーズやどのようなライフスタイル、ビジネスモデルを有しているのかがわからなければ、正しく接点を得られないためです。
ターゲットの情報を把握するための方法は、非常に豊富です。ターゲットが企業であれば、その領域の企業のコーポレートサイトを見比べてみたり、新聞などから業界の情報を常に追いかけたりすることで、ターゲットに入り込む余地を見出せます。
ターゲットが消費者の場合も、インターネットを活用した情報収集が効果的です。GoogleやYahoo!JAPANなどの検索エンジンに、自社商品やターゲットに関連するキーワードを入力してみましょう。検索されている関連語や上位に表示される検索結果を参考にすることで、大まかなトレンドの動向をつかむことができます。
また、X(旧Twitter)などのSNSでキーワードを検索すれば、よりリアルタイムのトレンドを正確に追いかけることもできるでしょう。消費者のトレンドの移り変わりは非常にダイナミックであるため、アタックリスト作成後も情報収集を継続し、リストを最新の状態に維持することが大切です。
リスト項目を設計し情報をまとめる
ターゲットへアプローチするために必要な情報がある程度集まったあとは、実際にリスト作成を進めていきます。
リスト作成に際しては、あらかじめフォーマットとして必要事項をまとめておき、情報の質にばらつきが生じないようにすることが大切です。アタックリストに掲載しておきたい項目としては、次のようなものが挙げられます。
| アタックリストに記載する項目 ・会社名・氏名 ・性別 ・電話番号 ・住所 ・メールアドレス ・業種 ・アタックの結果 |
必要に応じて、これらの項目を設置しましょう。特に、実際にアタックしてどのような結果が得られたかという事後報告に関する「アタックの結果」は、別の営業担当者が同じターゲットにアプローチをかけてしまうリスクを回避したり、営業活動の進捗報告を効率化したりすることに役立つため、設けておいて損はありません。
具体的な会社や消費者の情報を集めるうえでは、調査企業が独自に収集しているデータベースを購入したり、担当者が受け取った名刺情報をデジタル化したりすることで、一つのリストへとまとめます。あるいは、企業への問い合わせ履歴からターゲット情報をピックアップし、リスト化するなどの方法も挙げられます。
入力ルールやフォーマットを統一する
アタックリストを正しく管理するには、英数字の全角・半角や企業名の表記ルールをあらかじめ決め、入力内容にブレが出ないように統一することが重要です。
特に企業名は、通称と商号が異なる場合があるため注意が必要です。例えば、アタックリストへ記載する企業名は商号に統一するなど、明確なルールを設けておくとよいでしょう。
また、企業名にスペース文字が含まれている場合も、扱い方を決めておくとスムーズです。登記上の商号と完全に一致する必要はありませんが、表記の揺れや重複データを防ぐことで、情報検索やリスト活用の際に混乱を招かずに済みます。
補足情報を記載できる項目を用意する
アタックリストには、企業名や連絡先などの基本情報だけでなく、営業活動のなかで得た会話の内容や、顧客の関心事を記録できる項目を設けておくと便利です。こうした補足情報を蓄積しておくことで、次回のアプローチの際にスムーズに提案内容を検討できます。
営業活動は一度きりで終わるものではなく、継続的に改善や提案が必要です。顧客の興味や過去のやり取りを記録しておくことで、より的確なアプローチにつなげられます。
リストに必要な情報を登録する
アタックリストを作成する際は、ExcelやGoogleスプレッドシートなどのフォーマットを準備し、収集した企業名や連絡先などの情報を入力していくのが一般的です。
また、そのほかにもリスト作成に便利なツールがあり、詳細は後述します。自社に合ったフォーマットを探してみるのもよいでしょう。
情報登録を進める際には、入力ルールを守りながら、手作業によるミスを防ぐように心がけることが重要です。正確で丁寧な入力が、営業活動の精度を支える基盤になります。
アタックリスト作成で意識すべきポイント
アタックリストの作成は、リストの内容が情報の羅列になってしまわないよう注意して行なう必要があります。ここでは、リスト作成の際に意識すべきポイントを解説します。
| ポイント ・情報収集は多角的に行なう ・ターゲットの分析は丁寧に行なう |
情報収集は多角的に行なう
1つ目のポイントは、多角的な情報収集を行なうことです。
特定の媒体に偏った情報収集を行なっていると、ターゲットについての十分な情報を集められなかったり、正確ではない情報をあてにして誤ったアプローチをしてしまったりすることになりかねません。
新聞やコーポレートサイト、SNS、調査機関の資料などへ広く触れることで、正しいターゲティングとターゲットへの適切なアプローチ方法を開拓できます。
ターゲットの分析は丁寧に行なう
2つ目のポイントは、ターゲットの分析を丁寧に行なうことです。
先ほどお伝えしたように、正しくターゲットをピックアップし、相手への理解を深めるためには、多角的な情報収集が大切です。ただ、どれだけ多くの情報を収集していても、情報を有効活用できなければ精度の高いリスト作成は望めません。
営業の効率化につながるアタックリスト作成を実現するためには、分析のためのフレームワークを用いることが効果的です。
分析のためのフレームワークは多岐にわたります。ターゲットの属性や特徴を可視化して分類する「セグメンテーション分析」や、ターゲットを商品の「カテゴリ(Category)」「テイスト(Taste)」「ブランド(Brand)」という3つの指標に分類し、購買予測を立てる「CTB分析」といったものもあります。
ターゲットのニーズを深いレベルで理解し、リストに掲載すべき企業や消費者の情報を厳選することが大切です。
アタックリストを効果的に活用する方法
作成したアタックリストをさらに有効活用するためには、次の4つの方法を実践しながら運用すると効果的です。
| 効果的に活用する方法 ・業種や企業規模ごとにリストを分類する ・効果測定と改善施策を繰り返し実施する ・情報は常に最新のものに更新する ・情報収集やリスト管理にツールを活用する |
業種や企業規模ごとにリストを分類する
アタックリストは、業種や企業規模、地域などの条件で分類しておくと、ターゲットに合わせた最適なアプローチが可能になり、営業効率を高められます。
ターゲットを絞り込んでいても、業種や業界が混在しているリストでは営業活動に無駄が生じることがあります。そのため、あらかじめフィルタリングして整理し、統一感のあるリストに整えることが重要です。
また、リストのボリュームが増えてくると、管理が煩雑になりがちです。そうした事態を防ぐためにも、分類や管理のルールを事前に決めておくと、作業負担を抑えながら効率的な活用ができるようになります。
効果測定と改善施策を繰り返し実施する
アタックリストは一度作成して終わりではなく、効果測定を行ないながら定期的に改善を加えていきます。
確度が高いと考えていたターゲットからあまり良い反応が得られなかったとなると、リスト作成の方法や営業のアプローチに問題があったことが考えられます。それを見直す機会を設け、修正することを仕組み化すれば、こういった事態が発生するリスクを最小限に抑えられます。
アプローチ結果を参考にしながら改善を進めることで、さらに効果的なリストの作成とターゲティングのノウハウを蓄積することができます。効果測定を積極的に行ない、リスト作成の精度を高めましょう。
情報は常に最新のものに更新する
アタックリストに掲載されている情報は、常に最新のものであることが大切です。最新の情報に更新されていないと、ターゲットの連絡先が変わっていたり、すでに競合製品を購入していて自社で成約を得られる見込みがなかったりするためです。
こういったアプローチの成果が見込めないリストを常用していては、成約率を思ったように高めることができず、営業担当者の成果改善につながりません。アタックリストはオンラインで管理し、リアルタイムで情報を更新できる仕組みを採用することが望まれます。
情報収集やリスト管理にツールを活用する
アタックリストをより合理的に作成するためには、手動で作成するのではなく、ツールを活用した作成へと移行することが理想的です。
手動でのリスト作成にはとにかく時間がかかるだけでなく、リスト作成にともなうターゲットの選定が担当者の主観に依存してしまったり、リスト作成でミスが発生し正しい情報を共有できなかったりといった懸念があるためです。
近年はリスト作成に特化したツールが複数登場しており、最新のデータベースから自動でリストを作成・更新してくれるものが増えています。大まかなリスト作成はツール活用によって自動化し、さらなる厳選を担当者が対応するというプロセスを採用すると効率的です。
アタックリストを運用する際の注意点

アタックリストは営業活動を効率化するうえで重要な役割を果たしますが、運用にあたっては気を付けるべきポイントもいくつかあります。ここでは、アタックリストを運用する際の注意点を解説します。
| 注意点 ・誤った情報や重複データを防ぐ ・管理負担を減らし運用をスムーズにする ・情報共有や連携体制を整える ・リスト作成をゴールにしない意識を持つ |
誤った情報や重複データを防ぐ
アタックリストを作成・運用する際には、誤った情報や同じ企業の重複登録がないか必ず確認することが大切です。
情報の不備や重複があると、営業担当者が同じ企業に繰り返しアプローチしてしまい、顧客への悪印象や営業ミスにつながるリスクがあります。こうした事態は企業の信用を損なうおそれもあります。
定期的なリストの見直しや一元管理を心がけることで、正確な情報を維持し、効率的な営業活動を支援しましょう。
管理負担を減らし運用をスムーズにする
アタックリストは営業活動を効率化するための重要なツールです。しかし、管理に無駄な手間がかかると、かえって営業活動の足かせとなり、人的リソースやコストの消費が大きくなってしまいます。
負担を抑えるには、管理項目を必要最低限に絞り込み、誰でも操作しやすいツールを活用することが大切です。例えば、複雑な入力項目や手順を減らし、誰でも迷わず入力・更新できる仕組みを整備することで、リストの運用がスムーズになります。
負担を最小限に抑える工夫を取り入れることで、営業活動に必要なリソースを有効に活用しながら、質の高い営業活動を進められるようになるでしょう。
情報共有や連携体制を整える
アタックリストは、チーム全体で情報を共有・活用できる環境を整えることが重要です。
担当者同士で認識にズレがあると、情報の齟齬が生じるおそれがあります。共有ドライブや管理ツール、社内ポータルサイトなどを活用し、チーム全体で同じ情報を確認できる仕組みを作りましょう。
ただし、重要な情報を扱うため、アクセス権や更新ルールをあらかじめ決めておくことが必須です。アタックリストの活用方法や運用ポリシーを、チーム全員に周知させることも忘れないようにしましょう。
リスト作成をゴールにしない意識を持つ
アタックリストは、作成することが目的ではなく、営業成果を上げるために活用することに意義があります。
営業担当者としてリストを作ることに夢中になりすぎると、件数ばかり多いリストや情報が散乱しているリストを作成してしまうケースがあります。こうしたリストはむしろ業務の効率を下げる原因となり、成果につながらないばかりか、担当者のモチベーション低下にもつながりかねません。
リストの件数や作業量にとらわれることなく、成果を意識した運用を常に心がけることが大切です。
アタックリスト作成に役立つツール
アタックリストを作成・運用する際は、目的や状況に合わせてツールを活用することがおすすめです。おもなツールの特徴や活用のポイントについて紹介します。
| 作成に役立つツール ・手軽に始められるスプレッドシート ・営業管理を効率化するSFA・CRM ・業界特化型のリスト作成サービス |
手軽に始められるスプレッドシート
スプレッドシートは、アタックリストを手軽に作成・共有できる便利なツールです。特にGoogleスプレッドシートやExcelであれば、複数人でリアルタイムに編集ができ、フィルターやグラフ機能を使って情報を整理・分析することも可能です。
一方で、営業専用ツールではないため、入力ルールを決めて丁寧に管理することが欠かせません。スプレッドシートを活用する際は、管理面の工夫も取り入れるようにしましょう。
営業管理を効率化するSFA・CRM
SFAやCRMは、営業活動や顧客情報を一元管理できるツールで、アタックリストの作成や運用を効率化できます。
リード(見込み客)や商談の進捗状況、過去のアプローチ履歴などを記録・共有できるため、戦略的な営業活動をサポートします。さらに、アタックリストの管理だけでなく、適切なタイミングでの再アプローチや営業戦略の見直しなど、営業全体の質を高めるのに役立つツールです。
業界特化型のリスト作成サービス
業界や地域に特化したリスト作成サービスを活用すれば、自社で一から調べる手間を省き、精度の高い営業リストをスピーディーに入手できます。最新情報に基づいたターゲットリストを短時間で作成できるため、営業活動の効率化や人的コストの削減にもつながります。
ただし、こうしたサービスを利用する際は、提供元の信頼性やデータの更新性をしっかりと確認し、質の高い情報を活用することが大切です。
まとめ
アタックリストは、営業活動の無駄を省き、確度の高いターゲットに集中してアプローチするために重要です。
市場環境や競合状況を分析し、自社の営業課題を洗い出したうえで作成されたアタックリストは、営業効率を大きく高めることができます。さらに、作成したリストを常に見直し、最新情報へ更新しながら活用することで、成果を生み出す土台を整えられます。
こうしたアタックリストの運用をさらに強力にサポートするのが、専用ツールの活用です。
なかでも「HRコボットfor営業リスト」は、人材派遣会社に特化し、中途メディア・APメディア・その他の求人メディアから、市場の80%をカバーする求人情報をもとに営業リストを作成できます。出稿金額や業種、職種、キーワードなど、細かい条件を設定できるため、自社の営業方針に合った精度の高いリストを短時間で用意できます。
営業活動の効率化を加速させたい方は、ぜひ「HRコボットfor営業リスト」の活用をご検討ください。